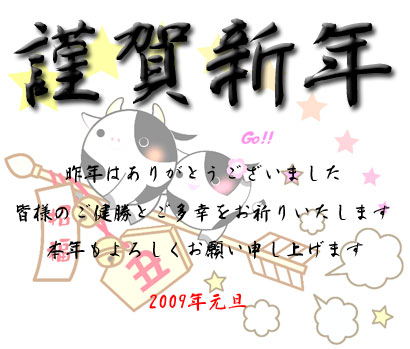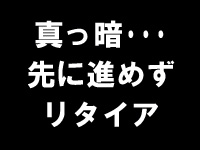JR生瀬駅を出発し武田尾方面へと進むと、福知山線の高架をくぐり、国道176号線に出る。左折し国道沿いの歩道を歩くのだが、この歩道が非常に狭い。場所によっては人がすれ違うのも大変なほどである。
対向車線側にあるガソリンスタンドを過ぎたあたりに、歩道左斜面に踏み跡がある箇所がある。ここが廃線間もないころは、この場所が廃線跡への入口だったとのことである。踏み跡を登るとすぐに
廃線跡である。ここからわずかではあるが
廃線跡を辿ることができるが、すぐ先で工事を行っているので、国道へと戻ることとなる。
工事現場の横を通り過ぎるが、この工事現場の箇所が一昔前までの廃線跡への入口であり。2年前に訪れた時には
JR西日本の警告板もこの場所にあった。
現在の廃線跡への入口は中国自動車道の高架の少し先で国道から離れ右前方へと道が下っている箇所である。国道沿いの
「木の元地蔵尊霊場」の看板を目印にすると良い。
いよいよ廃線跡を歩くことになる。最初の橋梁すぐ手前に
JR西日本の警告板が新しく立てられている。橋梁を渡ってすぐの所に、
信号装置かと思われるものが残っている。武庫川渓谷を眺めながら枕木の残る廃線敷きを進んでいくと、前方に最初のトンネルが見えてくる。
北山第一トンネルである。
北山第一トンネルの手前に
鉄の扉で覆われた箇所がある。鉄の扉の隙間から、中を垣間見ることができるが、ここは
掘りかけのトンネルである。また、ちょうどその扉の対岸の岩場に
鉄骨製の足場が組まれている。よく見ると足場から上へと梯子が架けられているのがわかる。何の為に架けられたのであろうか。北山第一トンネルを抜けてすぐに武庫川沿いを少し戻った所にも
掘りかけのトンネルがある。ここは柵や扉などもなく、
中に入ることもできる。このように掘りかけのトンネルがあることからも、当時の工事が困難を極めたことが推測できる。
北山第一トンネルの右側(武庫川沿い)が広く開いており、武庫川沿いをトンネルを抜けずに進むことができる。阪鶴鉄道開通時に通された線路跡であり、国鉄買収後に何らかの理由により、トンネルが掘られた。
北山第一トンネルを過ぎて進んでいくと、先週リタイアに追い込まれた、
北山第二トンネル。今日は、このトンネルを無事に通過、先に進むことができた。バラス石を踏む音がトンネル内に反響する中、足を止めると水の流れる音が聞こえてくる。しばらく進み、立ち止まると流れの音は、さっきより大きくなっている。静かに進んでいくとトンネルの
側壁の隙間から水が流れ出ているのを発見。
北山第二トンネルを過ぎると、
コンクリート製の小トンネルがある。これは滝よけとのことである。この先の3つ目のトンネルである、
溝滝尾トンネルを抜けると、おおきなトラス橋が架かっている。これが
第二武庫川橋梁である。第二武庫川橋梁の本線部はフェンスがあり通行不可なので
本線横の保線通路を渡る。本線部は枕木が並んでいるだけで危険です。フェンスを乗越え本線上を歩いたとWEBに自慢げに書いている人がいる。こういうマナーを守れないハイカーが事故を起こすことにより、ハイキング道としての利用を黙認しているJR西日本も全面立入禁止にせざるおえなくなるのである。愚痴はさておき、第二武庫川橋梁を渡るとすぐに
長尾第一トンネルに入る。長尾第一トンネルを抜けると今までとは違い、武庫川の右岸を歩いているのに初めて気づく人が多いのではないだろうか。第二武庫川橋梁は、その名の通り武庫川を渡る為に架けられた橋梁であり、第二武庫川橋梁を境に廃線跡は武庫川の左岸から右岸へと移るのである。
長尾第一トンネルを抜けて少しいった所の山側の
石積みの壁に通路があり、ここを潜った場所は改修工事を行っていた朝鮮労働者が昭和4年の3月26日の朝、ダイナマイトが氷結して爆発しないため、たき火で暖めていたところ引火、突然爆発し、二名が死亡、三名が重軽傷を負ったという悲惨な事故が起こった場所である。ハイカーの中には、事故をを知らない人が多いからだとは思うが、この場所をトイレとして利用していると聞いたことがあるが、事故現場なのでやめておくように。
長尾第一トンネルから先は、途中に桜の園や親水広場などもあり、宝塚市によって整備されている。この後、
長尾第二・
第三トンネルと2つのトンネルを残すが、どちらも、さほど長くなく、足元に気を付けて歩けば照明がなくても歩行可能なほどである。程なく廃線跡(地道)は終わりを告げ、
舗装道へと変わりJR武田尾駅へと向かうことになるが、実はこの舗装道も廃線跡である。現JR福知山線の高架の下を通り、
武庫川沿いに道場へと続いていくのである。
舗装道をJR武田尾駅に向かい歩いていくと。右側に
古井戸がある。この古井戸のところが、馳渡山(かけわたりたま:289.4m)の取り付きである。古井戸から明確な踏み跡があるので、踏み跡に従い約20分登っていくと馳渡山の
三等三角点に辿り着く。この馳渡山の下を現JR福知山線の第一武田尾トンネルが通っている。往復で40分ほどなので、廃線ハイクの後(武田尾から歩く人は前に)立ち寄ってみてはいかがだろうか。